【全図解】RSIの使い方!4つの売買サインの見方!
RSIの意味
使い方・見方

RSI(Relative strength index:相対力指数)は、
オシレータ系指標の中で、
代表的なテクニカルチャートです!
同じオシレータ系の
「サイコロジカル・ライン」の、
「上昇は、上昇としか捉えられない」
という欠点を、カバーしており、
非常に多くのトレーダーに多用されています。
今回は、このRSIを、
「どのように算出されるのか」
という原理と
一般的な「売買」見方を
紹介していきます!
RSIの計算方法

RSIの計算方法
RSIは、オシレ―タ系の為、
株価の買われ過ぎ、
売られ過ぎを判断する指標です。
そのために、
「指定した期間中の
値動きの中での、値上がり幅の割合」を
計算式によって出しています。
また、その設定期間は、
日足であれば、14日を設定するのが
一般的と言われています。
例えば、ある期間の値動きについて、
上昇した合計額が「1000円」
下落した合計額が「600円」で
あった場合、
1000÷(1000+600)×100
=62.5
となります。
上昇幅と下落幅を合わせて
考慮して計算することで、
大きな上昇一日と、
小さな下落数日分とで、
同じ効果を得ることができ、
買われ過ぎ、売られ過ぎを
判断しやすくなっています。
【売買ポイント➀】
買われ過ぎ・売られ過ぎの
逆張り

RSIの買われすぎ・売られすぎ
RSIの基本的な見方として、
通常のオシレーター系指標のように、
「買われ過ぎ、売られ過ぎを判断する」
ことが、挙げられます。
RSIが、
20%から30%を下回ると、「売られ過ぎ」、
70%から80%を上回ると、「買われ過ぎ」
と考えるのが一般的です。
しかし、
大きなトレンドが出てきた場合、
RSIは買われ過ぎ、
または、売られ過ぎのまま株価が推移する
ことになるため、
単純に、「買われ過ぎだから売り」と
判断するのは危険です。
他のテクニカルチャートと
組み合わせしつつ、
利用するようにしましょう。
【売買ポイント②】
ゾーン・エグジット

RSIのゾーン・エグジッド
買われ過ぎゾーン、
売られ過ぎゾーンから、
「出てきたとき(エグジット)」を、
1つの売買ポイントとして見る方法です。
売られ過ぎゾーンから、
出てきたときを、「買いタイミング」、
買われ過ぎゾーンから、
出てきたときを、「売りタイミング」
として、売買の判断材料として利用します。
投資の格言でよく言われる、
「頭としっぽはくれてやれ」の言葉通り、
「買われすぎ(売られ過ぎ)の状態から
抜け出す」のを見てから、
売買サインの一つとする方法です。
しっかりと、
売られ過ぎている状態から
反発し始めてからエントリーをするため、
ある程度流れを確認しているため、
ある意味、順張り的な方法と
考えることができます。
【売買ポイント③】
センターライン・ブレイク

RSI-センターライン
RSIの50%を「センターライン」とし、
これを抜ける時を、
売買タイミングとして扱う方法です。
このセンターラインを抜けるときに、
トレンドが発生しやすいとされており、
RSIがセンターラインを
上抜けるときを、「買いタイミング」、
下抜けるときを、「売りタイミング」と
して、売買の判断材料とします。
ダマシを防ぐために、
センターラインではなく、
55や60に設定する場合もあります。
【売買ポイント④】
「ゾーン・エントリー」
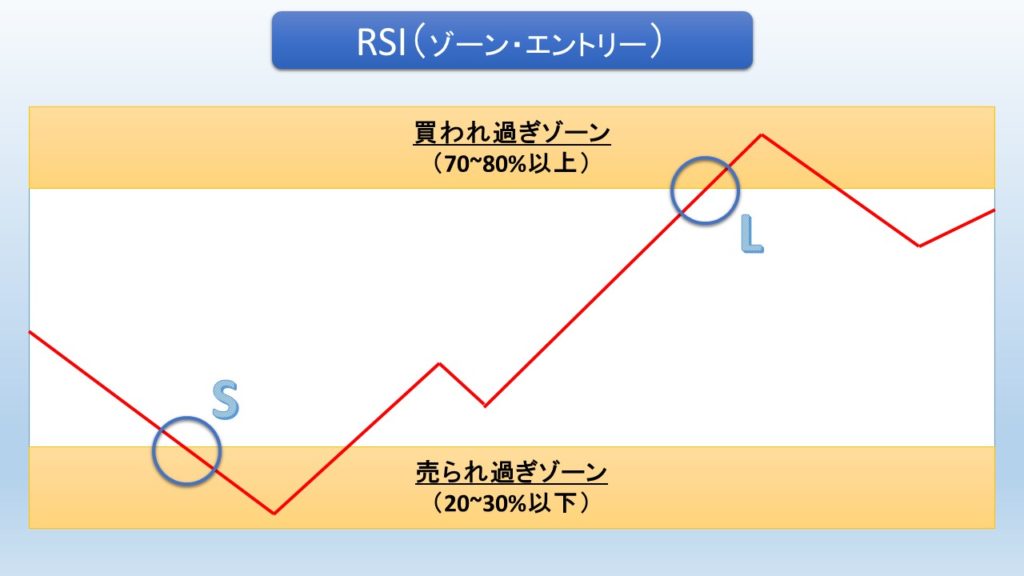
RSI-ゾーンエントリー
買われ過ぎゾーンに
入ったら「買いのタイミング」、
売られ過ぎゾーンに入ったら、
「売りのタイミング」
という、そこは反発ではなく、
その方向へのトレンドの開始と
考える売買方法です。
大きなトレンドが出てくるときには、
RSIは、買われ過ぎゾーン、
売られ過ぎゾーンで推移するという、
RSIのある意味欠点の部分を利用した
売買タイミングの方法で、
売買ポイント➀の買われ過ぎ、
売られ過ぎといった判断や、
②の「ゾーン・エグジット」と、
正反対の考え方になります。
【まとめ】

RSIは、一定期間の値動きの中野、
値上がり幅の割合で計算する、
オシレ―タ系テクニカルチャートで、
- 上下20~30%での、相場の過熱
- ゾーン・エグジッド
- センターライン・ブレイク
- ゾーン・エントリー
という主な売買サインがあります。
オシレータ系であるため、
他のテクニカルチャートとの
組み合わせが必須となります。
ちなみに、
「ボリンジャーバンド」との
組み合わせが有名です。
このボリンジャーバンドと、
RSIの組み合わせ売買も、
当サイトで紹介していきます。
RSIの、
本質的な理解をしたうえで、
実際にシュミレーションを行い、
様々な売買スタイルを、
試してみてくださいね!!
